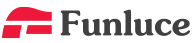中国、大連に在る「ファンルーチェ社」
 (工場棟)
(工場棟)
皆様方のお陰で、弊社ファンルーチェもこの9月で操業11年目を迎える事ができました
そこで改めて弊社が操業当時から目指してきた事やこだわりを第三者を交えて述べていこうと思います
当初から「セレンゲティ」「パタゴニア」はキャンピングカーのプレステージとなることを目指して開発されました
しかし、そこにはこだわりがあり中国工場を稼働させる事により、従来からある日本ののキャブコンバージョンと比べても価格を抑え高価格車にならぬ事を目指しました
それにはベース車の価格が高く,また通常のシャーシを持つ車両(トラック)と比較して手間のかかるスペースフレーム工法を採用しているにも拘らず人件費の削減、むやみなモデルチェンジをしない等の努力の結果、納得の価格、「適価」での日本国内での販売を可能にしています
ここからの青文字はキャンピングカーに興味のある第三者の「つぶやき」です
専用のスペースフレームを組付ける工法は、平面パネル工法と違い手間がかかることは承知しています
更に厳寒地での断熱性を考えて、断熱材にも独立発砲のクロロプレインゴムを使用するのもグラスウールなどとは違い、その点でも加工が面倒になるかと思います
その他にも、細かいところの仕上げを見ると、手が掛かっている様子がうかがえます
またこの商品に関しましては,オプション無しの状態でも、そのまま「くるま旅」出かけられる様に必要にして十分な装備設定を行なっています
荷重分布につきましては,セレンゲティ及びパタゴニアでは平均して前輪45%,後輪55%としています
また後輪用のサスペンションも架装後の重量に対応する様に増しリーフしてあります
↑この前後重量配分には驚きました。 BMWにも迫る勢いですね
平均(?)と書かれていますが、なんにせよすごいことです
前後どちらかのタイヤに荷重が集中することもないわけですね
又、構造に関してですが,スペースフレームの架装部分は運転室の天井に溶接されているだけではありません
切断されたベース車のBピラー部分には応力の集中を避けるためのガセット(補強鉄板)が溶接され,後部のスペースフレームに加わった応力をバランスよく受け持たせる構造となっ ています
↑Bピラーというのは、前席と後席の間の、屋根を支えている支柱のことです
ガゼットというのは、フレーム(棒)の接合部に、補強のために溶接された板等のことです
これにより、主に棒の接合面にのみ掛かりやすい負荷を分散させているということですね
改造後に残されるベース車の構造部材にかかる応力分布の数値が,ボディに手を加える前の状態で発生しうるものとほぼ同程度(この場合の負荷条件は両者とも同様とします)の状態となるまでバランスがとれるようになっています
さらに鋼製スペースフレームに対し,ある程度の弾性を持たせたFRP製のシェルを接着することにより,補助的な面強度も持たせてあります
↑これは家で言う2×4工法を考えればいいのでしょうか?
フレームは組んでいますが、パネルも強度担当部材ということですね。要するに柱構造と壁構造(2x4)の両方の良いとこ取りって事ですね
なお車体側面におけるキャブとシェルとの接合部ですが,この部分に外観と同様のデザイン(ボディやフェンダーのプレスライン)を持つ構造体を接合しているのは弊社の製品をなお一層美しいシルエットに仕上げています
↑この仕業ははベース車と架装したキャビンとが一体感が出る部位です
オリジナルシャーシとスペースフレームという、構造強度の違うもの同士がくっついているところですから、単純なパネルやフレームの溶接のみでは、捻りに対応することは無理だと思われます
ここを構造物にしているところに、ファンルーチェの技術力と、コストより品質重視の姿勢が伺われると思います
弊社でお客様向けに作成している商品カタログにもスペースフレームの写真を掲載しておりますが,これは細部のブレスおよびガセットを取り付け後の段階を撮影したものです
基本骨格を公開としているのは詳細な構造を企業秘密とせず,写真を見て納得していただくのを目的にさせていただいております
企業として,他社製品との違いとなる箇所を公開することは弊社の安全性にこだわり手間を惜しまない姿勢をお見せしたかったからです
今後も、大いに販売が期待されるキャンピングカーのキャブコンクラスにおいて他社との絶対構造の違いで他社との差別化をしていきたいと考えています
そしてその後、名キャンピングカー「ヨセミテ」の開発へと進化していくことになっていきます
ここで改めて弊社の社是
『 最新 最高よりも 最適を 』
を掲げ、今回はここで終わりとさせていただきます
以上、ファンルーチェ広報部からでした